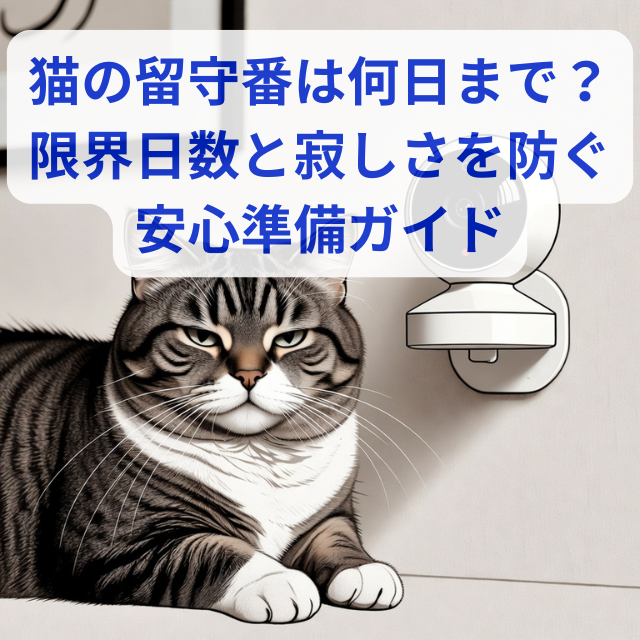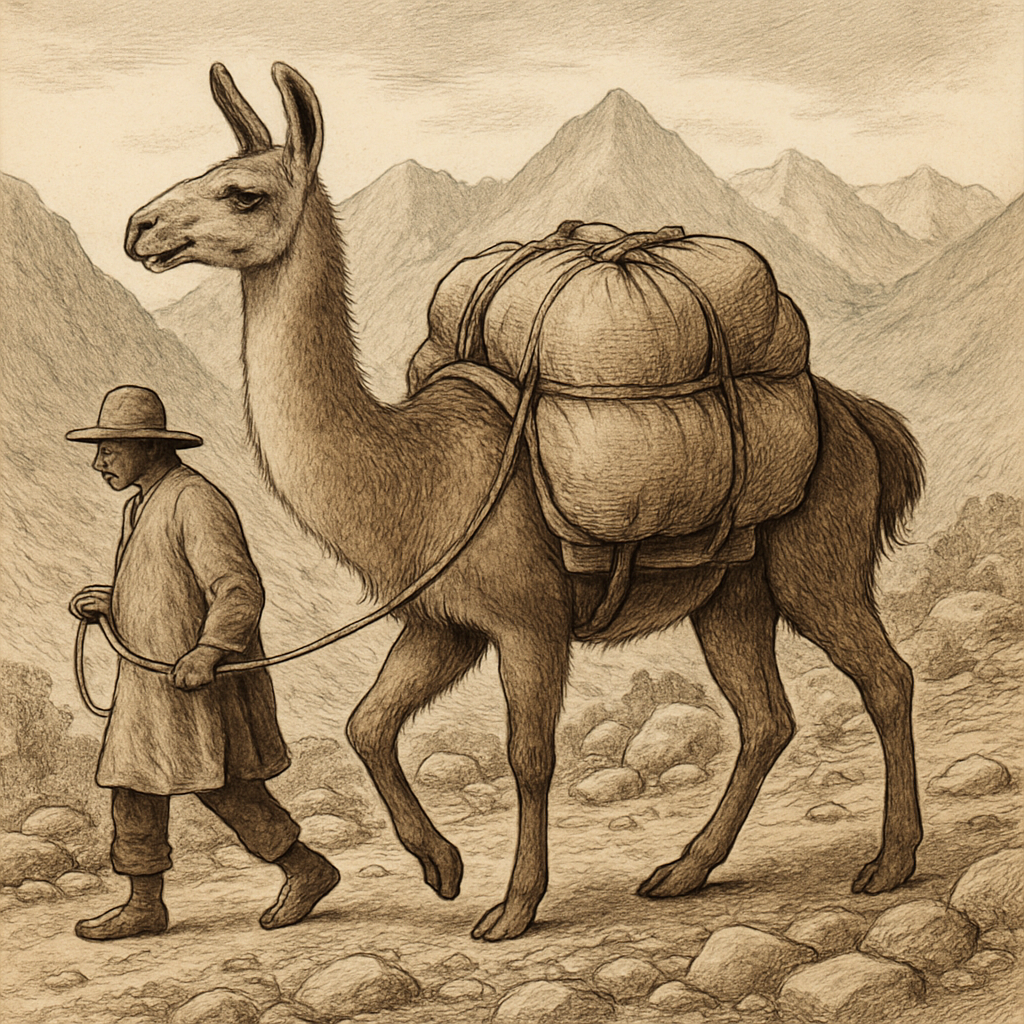「アンデスの歌うネズミ」と呼ばれるデグー。最近、日本でもペットとして人気が高まっているこの小動物について、もっと詳しく知りたいと思っている方も多いでしょう。
この記事では、デグーの魅力や特徴、鳴き声の意味、飼育のコツなどを分かりやすく解説します。
この記事を読むことで分かること
- デグーの基本的な生態と特徴
- デグーが発する様々な鳴き声の意味
- デグーにまつわる意外な豆知識
- デグーを飼育する際のポイントと注意点
デグーとの生活をより豊かにするための情報をお届けします。これからデグーを迎えようと考えている方も、すでに飼っている方も、ぜひ参考にしてくださいね。
デグーの生態と特徴:アンデスの歌うネズミの秘密
南米チリ原産のデグーは、「アンデスの歌うネズミ」という可愛らしい愛称で親しまれている小動物。ネズミに似た見た目をしていますが、実は全く別の生き物なんです。
多様な鳴き声でコミュニケーションを取る社会性の高さや、人に慣れやすい性格から、最近ではペットとしての人気がどんどん高まっています。さあ、そんな魅力的なデグーの基本的な生態と特徴について、詳しく見ていきましょう!
デグーの基本情報と生息環境
デグーは生物学的にはげっ歯目デグー科デグー属に分類される小動物です。よくネズミやチンチラと比較されますが、実は全く別の生き物なんですよ。
南米チリのアンデス山脈に生息していて、標高約1,200mの地域で暮らしています。この高さ、日本でいうと群馬県の草津温泉や栃木県の中禅寺湖と同じくらい!
野生のデグーは地面に巣穴を掘って生活し、1~2匹のオスと数匹のメスで構成される家族単位で群れを作り、縄張りを主張しながら社会生活を送っているんです。
デグーの主な特徴
- 完全な草食動物(ネズミは雑食なんですよ)
- 歯はオレンジ色(ネズミの歯は白色です)
- 基本は昼行性だけど、暑い時期は夕方や夜に活動することも
- 寿命は平均7~10年程度と小動物の中では長生き!
- 妊娠期間は約90日で、平均6匹の赤ちゃんを出産します
デグーは急激な温度変化に弱く、特に暑さに弱いという特徴があります。これはアンデス山脈という気温の年較差が小さい環境で進化してきたからなんですね。
デグーの「歌うネズミ」と呼ばれる理由
デグーが「アンデスの歌うネズミ」と呼ばれる最大の理由は、その豊かな鳴き声のバリエーションにあるんです!なんと、デグーは15~20種類もの異なる鳴き声を使い分けて、仲間や飼い主とコミュニケーションを取ります。
これはデグーの高い社会性と知能の表れでもあるんですよ。
デグーの主な鳴き声とその意味
- 「ピルッピルッ」:落ち着いているときや嬉しいとき
- 「ピッピピッ」:リラックスしているときの別バージョン
- 「キュー」:不安や恐怖を感じているとき(この時は安心させてあげましょう)
- 「プキュプキュ」:お腹が空いているとき(ごはんをねだっているんです!)
- さえずるような「ピピッ」:寝言を言っているとき(かわいいですよね)
また、デグーは人に慣れやすく、飼い主の呼びかけに反応したり、自分の名前を覚えたりする賢さも持っています。慣れてくると名前を呼ぶと近づいてきてくれるので、とっても愛嬌があるんですよ!
デグーの鳴き声は個体によって間や声の高さが若干異なり、とても個性的です。この多様な鳴き声を使って、デグー同士のあいさつ、求愛、威嚇、グルーミング時など、様々な場面でコミュニケーションを取っているんです。
この豊かな「言語」を持つことが、デグーが「歌うネズミ」と呼ばれる理由なんですよ!
デグーの知能と社会性
デグーは非常に知能が高く、社会性に富んだ小動物なんです!野生では家族単位の群れを形成し、複雑な社会構造を持っています。
この高い社会性は、ペットとして飼育する場合にも表れます。デグーは基本的に群れで生活する動物なので、できれば多頭飼いがおすすめ。
デグーの知能と社会性に関する特徴
- 自分の名前をしっかり認識できる賢さ!
- 飼い主を覚え、呼ぶと嬉しそうに近づいてくる
- 愛情表現として甘噛みをすることも(痛くないですよ)
- 複雑なコミュニケーションができる社交家
- ケージの扉の開け方を覚えるほど頭がいい!
デグーは人に慣れやすい性格ですが、完全に懐くまでには少し時間がかかります。特に生後3ヶ月以内の若いデグーの方が人に慣れやすいと言われていますよ。
また、デグーは好奇心旺盛で活発な性格をしているので、ケージ内には遊び道具や隠れ家、砂浴び用の容器などを用意してあげると喜びますよ!
デグーの鳴き声の種類とその意味を徹底解説
「アンデスの歌うネズミ」と呼ばれるデグーは、実に豊かな音声コミュニケーション能力を持っています。研究によると、デグーは15種類以上もの異なる鳴き声を使い分けることができるんです。
これらの鳴き声は、喜びや不安、警戒などいろんな感情を表現するだけでなく、仲間や飼い主さんとのコミュニケーション手段としても大切な役割を果たしています。さあ、デグーの代表的な鳴き声とその意味について、一緒に見ていきましょう!
警戒や威嚇を表す鳴き声
デグーが警戒したり、威嚇したりする時には特徴的な鳴き声を発するんです。これらの鳴き声は、デグーが不快に感じていたり、危険を感じていたりする時のサインなので、飼い主さんはしっかり理解しておくことが大切ですよ。
ワイン(Whine):軽い警告のサイン
「ワイン」と呼ばれる鳴き声は、軽い威嚇や警告の意味を持っています。一般的には6回ほど連続して高く鳴いた後、低く鳴くパターンが多いんですよ。
これは「あっち行って!」という気持ちを表していて、オスもメスも使う鳴き声です。デグーがこの声を出したら、少し距離を置いてあげるといいかもしれませんね。
グローン(Groan):強い警告のメッセージ
もう少し強い警告になると「グロ―ン」という鳴き声になります。5回ほど連続で鳴いた後に低く1回鳴くんです。これは「あっち行けってば!!!」というより強い意思表示なんですよ。この鳴き声が聞こえたら、デグーが本気で警戒していると考えた方がいいでしょう。
グラント(Grunt):本気の威嚇
さらに強い警戒や警告を表す「グラント」という鳴き声もあります。これは「キーキー」や「プギー」と聞こえる大きな鳴き声で、3〜5回ほど鳴きます。ライバルのデグーに出会った時や、相手を撃退したい時に使われるんです。
この鳴き声を出している時は、手を出すと噛まれる可能性があるので要注意!多頭飼いの場合は、仲間同士でケンカをする時にもこの鳴き声で威嚇し合うことがありますよ。
社会的な絆を深める鳴き声
デグーは社会性の高い動物で、仲間との絆を深めるための特別な鳴き声も持っているんですよ。これらの鳴き声は、デグーの社会構造や個体間の関係を維持するのに重要な役割を果たしています。
チター(Chitter):親密なあいさつ
「チター」と呼ばれる鳴き声は、親密な仲間同士のコミュニケーションに使われます。鼻と鼻、または鼻と口が接触した時やグルーミング(毛づくろい)の時に出す声で、あいさつのような意味合いを持つんです。
この鳴き声によって、デグー同士の社会的な絆が深まるんですよ。飼い主さんに対しても、慣れてくるとこの鳴き声を出してくれることがあります。嬉しいですよね!
チャフ(Chaff):仲間探しの声
「チャフ」という鳴き声は、遠くにいる仲間を確認する時に使われます。年齢や性別に関係なく使われ、一般的には3回、多くて15回ほど連続で鳴くんです。
これは「誰かいるの?誰?誰なの?」という意味合いを持ち、群れの中での位置確認に役立っています。ケージの中でこの鳴き声が聞こえたら、「ちょっと寂しいのかな?」と思ってあげるといいですね。
トリルとラウド・ホイッスル:親子の絆
メスの親が子守をしている時には「トリル」という特別な鳴き声を出します。また、子供のデグーが巣から離れて不安を感じている時には「ラウド・ホイッスル」という鳴き声で、仲間の気を引いて巣に戻れるようにするんです。
これらの鳴き声は、デグーの家族構造を支える大切なコミュニケーション手段なんですよ。赤ちゃんデグーを育てている方は、ぜひ注目してみてくださいね!
不安や痛みを表す鳴き声
デグーは不安を感じたり、痛みを感じたりした時にも特徴的な鳴き声を発します。これらの鳴き声は、デグーが助けを求めていたり、不快な状況を伝えようとしていたりするサインなので、飼い主さんはすぐに対応してあげることが大切ですよ。
ウィープ(Wheep):恐怖のサイン
「ウィープ」という鳴き声は、周囲に怖いものがある時に発せられます。0.1秒ほどの短く強い鳴き方で、口を開け耳を後ろに倒して鳴くんです。通常は2回連続して鳴きますが、もっと多く鳴き続けることもあります。
主に子供のデグーが周囲に問題を感じた時に、大人のオスやメスに向かって鳴きます。この鳴き声を聞いたデグーは逃げたり隠れたり、じっと息をひそめたりする行動をとりますよ。飼い主さんは、何か怖いものがないか周囲を確認してあげましょう。
スクイール(Squeal):痛みや嫌悪の表現
「スクイール」は、嫌なことがあった時や痛い思いをした時の鳴き声です。子供のデグーが知らない大人のデグーに会った時や、噛みつかれたりした時に発するんです。
これは声で相手をびっくりさせて逃げるための鳴き声かもしれませんね。この声が聞こえたら、デグーが何か嫌な思いをしていないか確認してあげましょう。
ピップ(Pip):ちょっと痛いよのサイン
「ピップ」という鳴き声は、グルーミング中に相手が過剰に毛づくろいをして少し痛く感じた時に「ちょっと痛いよ」と伝える時に使われます。これらの鳴き声を理解することで、デグーの不快感や痛みにすぐに気づき、適切なケアをしてあげることができますよ。
デグーとのコミュニケーションがもっと楽しくなりますね!
思わず驚く!デグーにまつわる面白いトリビア集
南米チリ原産の小動物「デグー」。近年、日本でもペットとして人気が高まっているこの可愛らしい生き物には、知れば知るほど驚きの特徴がたくさんあります。
ここではデグーの意外な一面や、思わず誰かに話したくなるような豆知識をご紹介します。デグーの魅力をもっと深く知って、飼育している方もこれから飼おうと考えている方も、デグーとの生活をより豊かにしていきましょう。
3歳児並みの知能を持つ賢い小動物
デグーは小さな体に驚くほど高い知能を宿しています。なんと人間でいうと3歳の子どもくらいの知能を持つと言われているんですよ!
これはペット界でも特に賢いとされる犬とも大差のない知能レベルなんです。その高い学習能力から、「おいで」「おまわり」「お手」などの基本的な芸はもちろん、小動物には難しいとされる「ハウス」まで覚えることができます。
デグーの賢さを示す具体例
- 自分の名前をしっかり認識できる
- 飼い主の顔や声を覚え、呼ぶと近づいてくる
- ケージの扉の開け方を覚えてしまうほど器用(脱走防止対策が必要です!)
- 瓶のふたを開けたり、容器をサイズ毎に重ねたりといった道具を使った行動ができる
これだけの知能を持っているので、退屈させないように知的好奇心を満たす遊び道具を用意してあげると、デグーも喜びますよ。ただし、その賢さゆえに時には「脱走」という形で表れることもあるので、ケージの管理はしっかりと行いましょう。
「デグーは糖尿病になりやすい」は誤解だった
デグーに関する情報の中で、「糖尿病になりやすい」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?実はこれ、最新の獣医学的知見によると誤った情報なんです。この誤解が広まった背景には、2013年の研究報告があります。
デグーを含むヤマアラシ亜目の動物には、インスリンへの自然抵抗性があることが分子学的・組織学的に確認されており、ある操作によって短期間に糖尿病へと移行することから、ヒトの糖尿病研究のモデル動物として使われていました。このことから「デグーは糖尿病になりやすい」という情報が一人歩きしてしまったようです。
しかし、実際の臨床現場では、自然発生的な糖尿病のデグーに遭遇することはほとんどないとのこと。むしろデグーに多い病気としては、
- 過剰グルーミング(過度に自分の体を舐めて毛が抜ける)
- 不正咬合(歯の噛み合わせがずれる)
- 尾抜け(尻尾の皮膚が抜ける)
などが挙げられます。特に不正咬合は、ペレットを中心とした間違った食事が原因とされています。デグーの歯のメンテナンスには、かじり木ではなくチモシー(牧草)が適しているという情報も最近では広まってきています。
硬すぎるものを噛ませると、臼歯が上顎・下顎を圧迫して病気の原因になることもあるので注意が必要です。
デグーとの暮らし方:飼育のコツと注意点
「アンデスの歌うネズミ」とも呼ばれるデグーは、その愛らしい見た目と高い社会性から、近年ペットとして人気が高まっていますよね!デグーと楽しく健康に暮らすためには、いくつか知っておくべきポイントがあるんです。
適切な環境づくりや日々のケア、コミュニケーションの取り方など、デグーとの生活を充実させるためのコツと注意点をご紹介します。初めてデグーを飼う方も、すでに飼っている方も、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
デグーの適切な環境づくり
デグーが健康に過ごすためには、適切な環境を整えることが何よりも大切なんですよ!特に気温管理はデグーの健康に直結する重要なポイントです。
デグーはチリのアンデス山脈という特殊な環境で進化してきたため、温度変化に弱い特徴があるんです。デグーの適温は23℃~25℃、湿度は50%程度が理想的です。
夏の暑い時期はエアコンを使用し、冬の寒い時期はヒーターなどで温度調節をしてあげましょう。直射日光が当たる場所や隙間風が入る窓際などは避け、できるだけ温度変化の少ない場所にケージを設置するのがおすすめですよ!
また、ケージ選びも重要です。デグーは活発に動き回るので、広くて高さのあるケージを選びましょう。ステージや回し車などを設置して、十分に運動できる環境を作ってあげることが大切です。ケージの素材は、デグーがかじり癖を持つため、硬めの素材を選ぶようにしましょうね。
デグーの生活に必要なもの
- 広くて高さのあるケージ(お家の中でも運動できるように!)
- 砂浴び用の容器と砂(皮脂の調整やストレス発散に必要なんです)
- 巣箱(安心して休める場所があると安心します)
- 給水ボトル(毎日新鮮な水に交換してあげてくださいね)
- かじり木(歯の伸びすぎ防止に役立ちます)
デグーとのコミュニケーション方法
デグーは社会性の高い動物で、野生では群れを作って生活しているんですよ!そのため、飼育下でも十分なコミュニケーションを取ることが大切です。デグーとの信頼関係を築くためには、根気強く接することがポイントなんです。
まずは、ケージの外から声をかけるところから始めてみましょう。デグーの名前を呼んだり、優しく話しかけたりすることで、少しずつ人間の存在に慣れていきますよ。慣れてきたら、おやつを手のひらに乗せて差し出してみましょう。
デグーが人に慣れるまでには時間がかかります。特に生後3ヶ月以内の若いデグーの方が人に慣れやすいと言われていますが、どの子も個性があるので、焦らずにゆっくりと信頼関係を築いていきましょうね!
デグーとのコミュニケーションで大切なポイント
- 毎日決まった時間に声をかける(「おはよう」「おやすみ」など)
- 名前を呼んで反応を見る(反応してくれると嬉しいですよね!)
- 手から餌を与える練習をする(少しずつ慣れていきます)
- 抱っこや撫でられることに少しずつ慣らす(焦らないことが大切)
- 「部屋んぽ」の時間を作り、一緒に遊ぶ(デグーも喜びますよ!)
デグーを抱く際は、下からすくい上げるようにして持ち、決して上から掴んだり、尻尾を持ったりしないように注意しましょう。デグーの尻尾は簡単に皮が剥けてしまう「尾抜け」という現象が起こることがあるんです。
デグーの健康管理と注意点
デグーを健康に長生きさせるためには、日々の観察と適切なケアが欠かせませんよ!デグーは小さな動物なので、体調の変化に気づきにくいことがあります。毎日の食事量や排泄物の状態、行動の変化などをよく観察してあげてくださいね。
デグーの食事は、主食として牧草(特にチモシー)を常に十分な量を用意し、副食としてデグー専用のペレットを与えます。ペレットの量は体重の約5%が目安です。デグーは糖尿病になりやすいと言われていたこともあり、果物や野菜などの糖分の多いものは与えないようにしましょうね。
また、デグーの歯は一生伸び続けるため、不正咬合になりやすい特徴があるんです。チモシーなどの繊維質の多い牧草を十分に与え、歯が伸びすぎないようにケアすることが大切ですよ。ケージの金網を頻繁にかじる、餌をこぼしながら食べる、よだれが多いなどの症状がある場合は、不正咬合の可能性があるので、早めに動物病院を受診してあげてくださいね。
デグーの健康管理で注意すべきポイント
- 室温管理(23℃~25℃が適温です!暑すぎると危険です)
- 適切な食事(主食は牧草、副食はペレット。バランスが大切ですよ)
- 砂浴びの環境整備(1日1回程度。デグーにとっては大切な習慣なんです)
- 歯の健康チェック(伸びすぎていないか定期的に確認してあげましょう)
- 尾抜け防止(尻尾を絶対に掴まないでくださいね)
- 大きな音を立てない(デグーはびっくりしやすいんです)
- 「部屋んぽ」時の危険物(特に電気コード)の管理(かじられると危険です!)
まとめ
デグーについて、生態から飼育方法まで幅広くご紹介しました。
デグーの魅力まとめ
- 南米チリ原産の社会性の高い小動物
- 15種類以上の鳴き声を使い分ける高いコミュニケーション能力
- 3歳児並みの知能を持ち、名前を覚えたり簡単な芸を覚えたりできる
- 適温は23℃~25℃で、特に暑さに弱い特徴がある
- 主食は牧草(特にチモシー)で、歯の健康維持に重要
デグーとの暮らしでは、適切な環境づくりとコミュニケーションが大切です。デグーの鳴き声や行動の意味を理解することで、より深い絆を築くことができるでしょう。これからもデグーとの時間を大切に過ごし、その魅力をさらに発見していってくださいね。